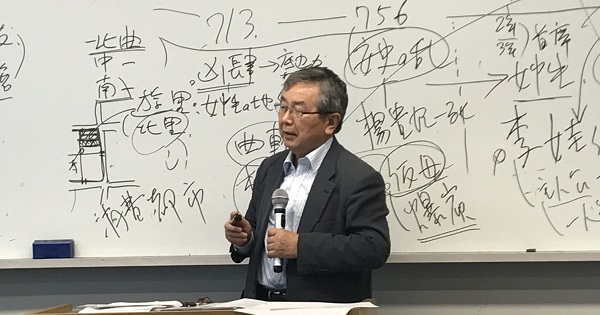「ロシア語は語順がないので、ロシア語を始めようという方にはぴったりです」
大学入学の際、第二外国語を選ぶ際のガイダンスである。そうか、語順がないのか…。
英文法と聞くと、一ミリのミスも許されず、完全無比な正確性を求められた私は、ロシア語を学習することに非常に魅惑的に映った。偶然だが、戦時中、祖父がソ連の捕虜で捕まっていたことも何かの縁に感じた。
初回の授業は前評判通り、「マドンナ教授」の名前が似合う、美形の先生だった。教え方が丁寧で、実に分かりやすい。しかし難点は格変化。男性名詞、女性名詞、中性名詞、実に18種類もあり、それら全てが男性、女性、中性の区分けがされなければならなければならなかった。
ガイダンスじゃ一言も格変化があると言わなかったのに…。何だか騙されたような気分だった。
とは言え、ロシア語は受講者が少ないこともあり、どこか和やかな雰囲気だった。「ロシアに行けば単語さえ話せば十分通る」と話す教授がいたり、まだ教材が整備されておらず、何故か妻が亭主の尻に敷かれ続ける模範テキストをカセットテープで聴いていたりした。カセットテープは決して音質は良くないが、どこか異国情緒を思わせ、「ロシアってどんなところなんだろう?」と思いを馳せたりした。ロシアはバレエや演劇が盛んな国柄だ。暇さえあれば詩を生みだし、弾圧に遭いそうものならアニェクドート(皮肉)を考えるイメージだ。そんな少々根暗な国民性や文化の源泉にどっぷりと浸かってみたい。そう思い、ロシア語ロシア文化専修に進むことにした。
露文科と聞くとロシア語がかなり話せる印象だが、決してそんなことは無かった。幸い、第二外国語のロシア語選択者が少なく、ロシア語選択者以外にも積極的にロシア語ロシア文化専修を受け入れていた。
こうして、ロシア語ロシア文化専修は計8名でのスタートだった。2年次では「まずロシア語の基礎を叩き込む」といったことは一切無く、相変わらずアットホームな雰囲気だった。
著名なロシアの演出家が演出ノートを借りて、日本語に翻訳してみる、といった授業が日々行われていたり、ロシア思想史では、ある一人の人物を取り上げ、教授がまるで知り合いのように「この人はホントに気難しくてねえ…」と楽しそうに喋り出したりと、どこか家庭的な雰囲気を感じさせた。ともすれば、「これを世の中にどれだけ還元できるか」という合理性より少し隔絶した、「そもそも文学とは?」ということの、物事の本質を追求出来たような気がする。
残念ながら18種類の格変化は未だに忘れてしまった。しかし、ロシア人に宿題で課されたロシアアニメの歌ははまだ思い出すことも出来、不思議な縁を感じる。
そろそろ冬だ。ロシアはきっと寒いだろう。嘘か誠か分からないが、冬場では酔っ払い過ぎてウォッカで倒れて凍死した人を何人も見掛けると聞く。きっと迷信だろう。演出ノートを日本語に翻訳している際、黒いシミがあり、教授が事もなげに「ああ、たぶん俳優が演技に怒って、ボールペン折った跡ですね」と言いだしてきて、そういうところがロシア人を嫌いになれないと思う瞬間である。
(編集室が文字の修正、タイトル付けをしています)